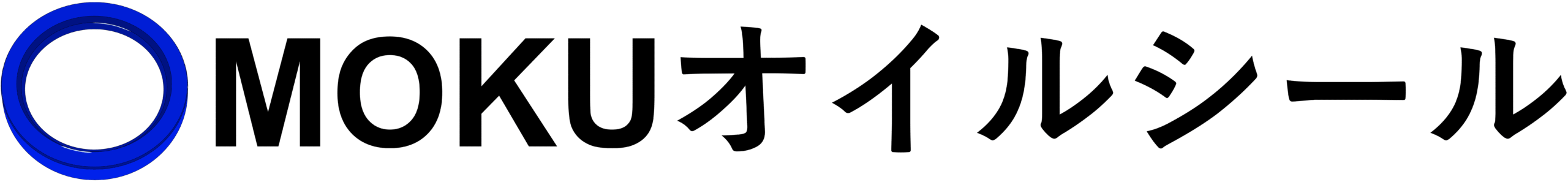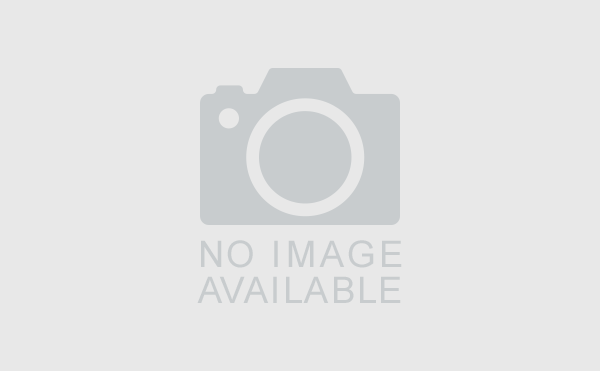オイルシールの主リップ先端温度の低減方法
主リップ先端温度の上昇による弊害
オイルシールの主リップ先端温度が過度に上昇すると、様々なトラブルを引き起こす要因となり、別記事でもご紹介したオイルシールの漏れ要因にも直結します。オイルシールは自動車やロボット、減速機など様々な機械・装置で使用されており、主リップ先端温度の上昇が起点となることで引き起こすトラブルの一例としては、以下があります。
① オイルシール漏れによる機械・装置の寿命低下/周辺環境の汚染
② 機械・装置内部のオイル/グリースの劣化
③ 機械・装置の効率低下(パワーダウンなど)
④ 機械・装置の故障・誤作動
⑤ 異音・異臭
よって、主リップ先端温度を低減することは機械・装置のトラブルを未然防止するためにも非常に重要となります。特に、上記①の「オイルシール漏れ」については、主リップ先端温度の過度の上昇によって、クラック、ブリスタ、主リップやシャフトへの固着物、ゴム硬化などの直接的な漏れ要因の発生を促進させることとなります。
本記事では、オイルシールの主リップ先端温度の低減方法について解説します。
主リップ先端温度に影響する因子と低減方法
オイルシールの主リップ先端温度の低減方法を解説する上で、主リップ先端温度に影響する因子について説明します。オイルシールの主リップ先端温度が高いということは、「オイルシールの摩擦トルクが高い」と言い換えることができ、摩擦トルクTは以下の式(1)で表すことができます。
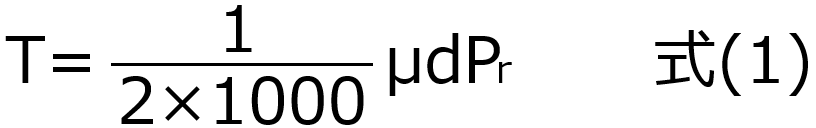
ここで、μ:摩擦係数、d:軸径、Pr:緊迫力 を意味します。
さらに、摩擦係数μを細分化すると、以下の式(2)で表すことができます。
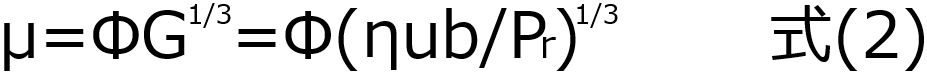
ここで、Φ:油膜状態/ゴム滑り性により定まる定数、η:密封媒体の粘度、u:周速、b:主リップ接触幅 を意味します。
以上より、主リップ先端温度に影響する因子としてはd, Pr, Φ, η, u, bの6因子が存在し、式(1), (2)より主リップ先端温度を低減する(=摩擦トルクを低減する)方法は以下となります。
(1) 軸径dを小さくする
(2) 緊迫力Prを小さくする
(3) 油膜状態/ゴム滑り性により定まる定数Φを小さくする
(4) 密封媒体の粘度ηを下げる
(5) 周速uを下げる
(6) 主リップの接触幅bを小さくする
上記の6つの方法によって、主リップ先端温度を低減することができます。ただし、(1), (4), (5)については、機械・装置の仕様によって決まるものであり、変更は困難となることが多く、オイルシール側で調整可能となる(2), (3), (6)で対応することが多くなります。その中で、(2)は単純に緊迫力を下げる対応となり、(6)は主リップバレル角の調整や耐摩耗性に優れたゴム材を選定するといったことが容易に思い浮かびます。
(3)については、各オイルシールメーカーでの研究開発による改良が進んでいます。一例として、コーティング技術があり、主リップ先端にテフロンコーティングなどを施すことで滑り性を向上させ、主リップ先端温度を低減することができます。また、主リップしゅう動面の粗さ(凹凸)について、粗さを大きくすれば油膜が厚くなることで主リップ先端温度は低減する傾向にありますが、密封性の観点では漏れを助長することにもなるため、各オイルシールの使用条件に適合する粗さ設定が必要となります。
※当方においても研究開発による(3)のノウハウ構築を行ってきました。
関連記事
以下の関連記事についてもご参照下さい。
【記事】【メーカー研究者執筆】オイルシール漏れ要因まとめ – MOKUオイルシール
【記事】オイルシールのクラック発生原因と対策 – MOKUオイルシール
本記事内容をご覧いただき、興味を持たれたり、『もっと詳細を知りたい』等と感じましたら、お気軽にお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。
【ご参考1】熱電対付きオイルシールについて
当方では、オイルシールの主リップ先端温度を直接的に測定することができる”熱電対付きオイルシール”の製作を請け負っています。お客様で保有するオイルシールを当方へ送付いただき、熱電対を主リップ先端のゴム中に加工し、納品とさせていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。熱電対の+/-を表記した状態で納品いたしますので、お客様では熱電対をロガーに接続いただくだけで主リップ先端温度の測定が可能となります。
【ご参考2】オイルシールの現品調査について
当方では、オイルシールの現品調査を請け負っています。お客様より調査対象となるオイルシール(希望される場合は軸も)を送付いただき、詳細調査を実施し、密封性を有する状態かを考察(漏れが発生している場合は漏れ原因を推察)して調査レポートを提出させていただきます。オイルシールのメーカーは問いません(どのメーカーでも対応いたします)。現品調査を実施し、オイルシールメーカーの研究部/品質保証部と同様の視点で見解・考察を提示させていただきます。